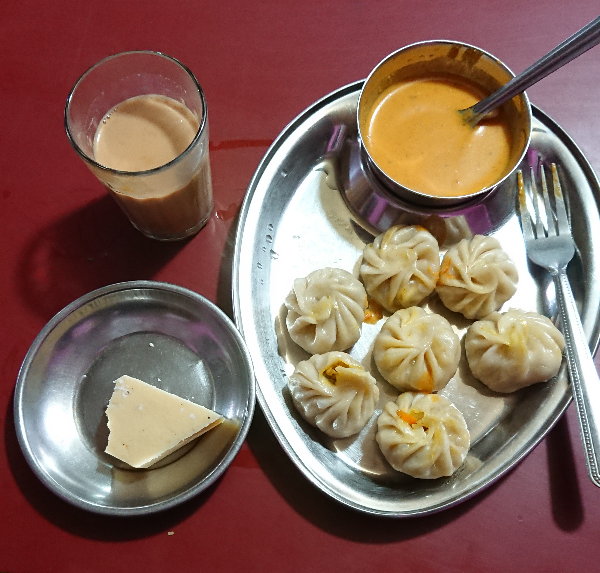2024年7月1日
当店のネパール側事務所がある古都バクタプルから東へバスで1時間の距離にバネパという町があります。ここもバクタプル同様にネパール中部に点在するネワール族の街です。
ネパールに50以上あるという少数民族のうちでもネワール族は人口が特に多いというほどでもない(上から6番目)のですがかなり栄えており、商売上手なためか交易路沿いに拠点を築き、飛び地のような街を作ってきたのです。
そこがネワールの街かどうかは見ればすぐに分かります。なぜならそこにはネワール様式と呼ばれる特徴ある木と煉瓦造りの街並みが広がっているからです。
こんな感じの建物です。

ネワール様式の家並
バネパは近くにあるドゥリケルやパナウティといったネワールの街とは違い、これといった見どころがないため観光客も素通りする街です。なので店長もいままで行ったことがありませんでした。
しかしそう遠くない上に幹線道路沿いにあって移動しやすいので、今回初めて行ってみました。目的は特にありませんが、ひとまずグーグルマップに表示されたお寺に行ってみようと思いました。
結構縮小して見てもマップに表示されているところからすると、大きくて立派なお寺に違いありません。
さてまずはバクタプルから東に向かうバスに乗ればいいのです。ただし少々慣れが必要です。一部の観光バスを除いてネパールのローカルバスはみんなそうなんですが、バスがバス停に止まったら車掌が素早く降りてきて行き先を叫ぶのです。
行き先は一つではないので主要な行き先を続けて連呼することになります。日本人には「じゅげむじゅげむごこうのすりきれ・・・」としか聞こえない長い口上を聞き取って、自分の目的地(またはその近く)が含まれていればそのバスに乗ってよいことが分かります。
大きなバスパークでもなければバスはひっきりなしにやって来てはすぐに走り去るので、聞き取りに許された時間は短ければ2,30秒です。なかなかに高いハードルなのです。店長も聞き取れるようになるまでずいぶんかかりました。
下の動画の車掌(黄色い服の兄ちゃん)が口にしている行き先は「ペプシコーラ、プラノティミ、サノティミ、サラガリ、バクタプル」なのですが、聞き取れますでしょうか?ちなみにペプシコーラも立派な地名です。

乗ってしまえばこんな感じ
バネパに着いても車掌が「バネパに着きました」と教えてくれるわけではありません。車掌はあくまでそこから先の行き先を叫ぶだけなのでスマホの地図でしっかり現在地を確認して降りましょう。
知らない街に着いたらまずトイレの位置を確認します。これ重要。日本ならちょっとしたお店や公園には必ずトイレが付いているのですが、ネパールではそうはいきません。田舎だとなおさらです。バネパのような大きな街ならバスパークの付近やショッピングモール(あればですが)が狙い目です。
トイレの位置を確認したら街をぶらぶらしながらお寺に向かいます。町を歩いての第一印象は『まるで20~30年前のバクタプルのようだ』です。時期が悪かったせいなのかもしれませんが観光地化されていないので自分以外の外国人は一人も見かけませんでした。お店も観光客に媚びることなく、英語のメニューなどありはしません。
極めつけは野犬の多さです。多いだけではなくフレンドリーではありません。こんな所までも昔のバクタプルそっくりです。野犬にとっては外国人など自分のテリトリーに不法侵入して来たただのよそ者でしかありません。久しぶりに吠えたてられました。
こんな時は石を拾うフリだけでもすれば犬は警戒して距離を取ります。小さいころから住人に吠えては石をぶつけられて育ってきたので自然にそうなったのでしょう。棒を手に持っても同じ効果があります。犬がビビっている間にテリトリー外へ逃げましょう。ただし走ってはいけません。走れば自分より弱い相手とみて追いかけてきます。あくまでゆったり歩いて離れます。
こんな状態で地元の人は困っていないのでしょうか?どうやら困っているようです。これも久しぶりに見ました。下の写真の人が何なのかお分かりでしょうか?

一分の隙も無い野犬狩りのコスチューム
これは野犬狩りです。長袖に長ズボン、靴は足首まである丈夫な革靴、そして何と言っても大きな網を持っているのですぐに分かります。後ろには毒物を抱えた助手とギャラリーの子供たちが控えています。
広い場所なら人間がどう頑張っても犬を捕まえるのは至難の業でしょう。走る速さが違いすぎるからです。ですが狭くて入り組んだネワールの町並みなら頭を使った連係プレイで挟み撃ちにしたり行き止まりに追い込んだりできる人間の方に分があります。
捕まえたら保健所まで連れて行くなどという手間はかけません。その場で毒を打ち込みます。殺すところはあまり子供に見せて欲しくないのですが…。
あまり近づいて巻き添えを食いたくないので横目で見ながら通り過ぎました。店長の目的はお寺なのです。
後編に続く....